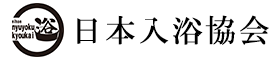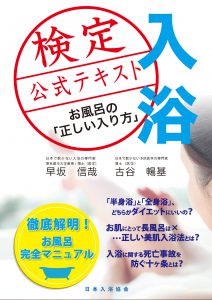銭湯の始まり
銭湯の始まり

寺院や僧侶たちによる入浴啓蒙事業が行われる中、その良さが伝わっていた人々から施浴への要望が高まっていったと思われます。一方で、奈良時代に始まった荘園制度(私有農地)の崩壊が中世に入って始まり、かつて裕福だった寺院の財政も苦しくなるところが出てきました。
そういった流れの中、今までは無料で開放されていた施浴に料金を課したことが、銭票の始まりの一つだと考えられています。東大寺でも、「浄財」という名目で一般庶民に湯屋の使用を許可した記録が残っているため、東大寺大湯屋は「現存するもっとも古い銭湯」という見方もあります。

東大寺大湯屋(写真:wikipediaより)
また寺院とは別に、公卿や武士、その他の裕福な個人の家では、入浴施設を有するようになっていました。人を招いて茶の湯やご馳走、お酒などをふるまいましたが、そのこと自体を「風呂ふるまい」と呼ぶことがありました。その理由はお風呂に入ってもらったあとに、宴を催すことが多かったからです。ちなみに、公卿の間では、裕福でお風呂がある家に「もらい湯」へ行った際、湯銭代わりに薪木を持ち寄ることを「合木風呂」と呼んでいました。
このような流れから、寺院の浴堂ではない場所に入浴施設を持って商売をするケースが出てきました。また寺院の施浴では、入浴に際しての堅苦しい規則があり、場合によっては遠くまで足を運ぶ必要もあったので、そのような町湯が歓迎されたのです。これが銭湯のルーツの一つといえるでしょう。
銭湯と思われる古い記録としては、ともに平安時代の公卿による日記である「永昌記」(1110年)、「中右記」(1129年)の両書に、京の中心部の一条に「湯屋」と称する商業施設があったことが記されています。

鎌倉時代には高僧の日蓮が書いだとされる「日蓮御書録」(1266年)には「御弟どもには常に不便の由有べし。常に湯銭ざうりのあたひなんど心あるべし。」とあります。日蓮が弟子たちの入浴料や草履代を気にしていることから、この頃には銭湯のようなものが存在し、そこに行くことが僧の日常で重要なことであったことが何われます。
さらに京都の八坂神社の記録書「祇園執行日記」(1321〜1326年)では『岩愛寺で銭湯風呂の事、今年よりこれを正月に立て始める。元享年中か、雲居寺寺領で銭湯あり。一一日、岩愛寺で銭湯風呂のこと、社領内の上の者のためにあり。」と寺院において営業された銭湯という文字がはっきりと見え始めます。
このような銭湯形式の入浴文化は、「和のサウナ」と同様、日本の中心であった関西地方以西に多く見受けられました。

みなさんも入浴専門家になれます!「入浴検定」挑戦しませんか?
第9回入浴検定は、オンライン試験で開催いたします。
パソコン、スマートフォン、タブレットからご受験いただけます。
≪開催日時≫ 2021年2月6日(土)
≪開催時間≫ 11:00~12:00
≪受検料金≫ 6,600円(税込)
≪合格基準≫ 正解率 80%以上
[maxbutton id=”4″ ]新商品が続々登場😍日本入浴協会★温 LINE STORE
→読むだけでもためになる!『入浴検定公式テキスト』ご購入はこちら!
(入浴のオンラインショップへ)